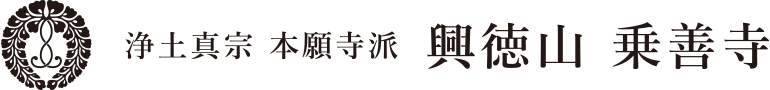新年度を迎えて二ヶ月余りが過ぎました。大きく環境が変わった方も多いことと思います。それほどの 変化がなかった方も、少なからず環境に変化があったことと思います。環境の変化に伴い、戸惑いや間違い 失敗なども起こるのではないでしょうか。指導を受けたり叱責を受けたりということもあるでしょう。 二宮尊徳の言葉に「可愛くば 五つ教えて 三つ褒め 二つ叱って良き人とせよ」というものがあります。( 余談になりますが、白石小学校正門奥に尊徳像があります)人を育てる上の、接し方のバランスのとり方を 示すものといわれています。しかし私たちの周りでは叱られる事が多い割に、褒められることが少ないよう に思われます。その人のことを思い、成長を願ってはいても、様々な理由でつい叱ることが先になってしまい、褒めることは後回しになってしまいがちです。時によっては全く褒めることなく終わってしまうこともよくあることでしょう。「教える、褒める、叱る」のバランスをとって人と接するのは本当に難しいことす
新聞の読者投稿欄に「男はつらいよ」の中で笠智衆さんが演じる、柴又帝釈天の住職・御前様が主人公の寅次郎たちに「人が褒め合うということは、これは実に良いことだね。お互いに褒め合わなきゃいけない。褒め合ってこそ人間は少しずつ向上していくんじゃないかな」と言葉をかける場面が紹介されていました。人は褒められたときに成長するのはもちろん、ここには褒めるほうも相手を褒めることによって成長することが明かされています。「褒め合ってこそ人間は向上する」。褒め合うこととは相手を認めることです。たとえ自分とは異なるところがあっても受け入れる寛容さを持つということです。
今、大小さまざまな対立、不寛容、匿名性に身を隠した誹謗中傷が、私たちのごく身近なところでも、世界規模でもおこっており、エスカレートしていく傾向にあります。この三月、札幌市議会が、多様性と包摂性のあるまちづくりを目指す「共生条例」を可決したのは記憶に新しいところであり、活発な議論の展開を促すことが期待されます。
浄土真宗の妙好人の言葉に「子ども叱るな来た道だもの 年寄笑うな行く道だもの」というものがあると聞いたことがあります。永六輔さんの著書『大往生』に愛知県のお寺の掲示板に有ったものと紹介されていますので、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。私たちの判断の基準は今の自分であり、昔の自分、これからの自分の姿に思いをいたし、判断し人と接することは難しいことでしょう。妙好人の言葉には褒める」とは出てきませんが、「𠮟る・笑う」を戒めることにより、相手を認める大切さを示しているものと受け止めることができます。
二〇一八年に出された「私たちのちかい」に「自分だけを大事にすることなく 人と喜びや悲しみを分かち合います 慈悲に満ちみちた仏さまのように」とあります。叱るよりは褒める、褒め合う上に認め合う、認め合った先に広がる分かち合う世界。私たち浄土真宗のみ教えの中に身を置くものは、この思いを大切に、人と接し、日々の生活を大切にそして有意義に過ごしていきたいものだと思うのです。
二〇二五(令和七)年 六月