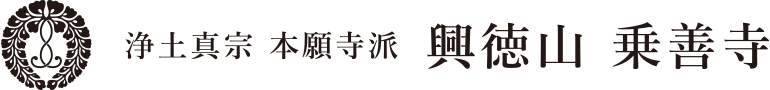今年の7月19日昼過ぎ頃、世界規模で約850万台のコンピューターが異常停止する事態が起こりました。原因になったセキュリティーソフトといわれるものは主に政府機関や大手企業で用いられているものでした。影響は交通、物流、医療、金融など多くの分野に及び、航空業界では世界中で5千便の欠航、4万便以上の遅延が余儀なくされました。テレビの放送が中断したり、裁判所飲食店などでも何らかの影響を受けたとの報告もなされています。アメリカの保険会社の試算では損害は2兆3千億円にも上るとされています。
紀元前300年頃に中国で戦国時代の思想家の荘子の著された『荘子』に、孔子の弟子で十哲の一人とされる子貢の故事が伝えられています。子貢が楚の国を訪ねた時に老いた農夫が畑に水を撒いていました。あまりにも能率が悪そうなのでハネツルベという水汲みの機械の事を教えました。
農夫はそれに対して「機械有るものは必ず機事(機械にたよる仕事)あり。機事有るものは必ず機心あり。機心胸中に生ずれば則ち純白備わらず。純白備わらざれば、則ち神生定まらず。神生定まらざる者は、道の載せざるところなり」ー(便利な機械を使って楽をしよう、得をしようという気持ち(機心)によって純白の心が失われると道を踏み外してしまう」と答えました。
私たちは技術革新によって以前より幸せになれたのでしょうか。確かに今の私たちは便利な機械のない生活は考えられません。しかしその便利さは一瞬にして崩れてしまう危険を抱えていることはこの度の出来事からも明らかです。
さらに続けて孔子が「農夫のいうことはもっともであるが、彼は一つを知っているけれど二つを知っていない、機械に頼りすぎること(機心)も、機械に頼りすぎることを恐れるあまり、かたくなにこれを否定することも、どちらかに極端に偏ってはいけない」と説いています。
私たちは日々の生活の中で、仏様の教えを親しく聞かせていただいていますが、その教えの基本の一つに『中道』というおしえがあります。
お釈迦様は菩提樹の下で悟りを開いた後、仏教四大聖地のヴァーラーナシーのサルナート鹿野苑で五人の比丘に対して最初の説法をされました。これを初転法輪といい、この時、四諦八正道と共に中道について語られたといわれています。(因みに他の3つの聖地は、誕生の地ルンビニー、悟りを開いたブッダガヤ、涅槃の地クシナガラ)。
「中」とは、たんに二つのものの中間ということではなく、両極より離れることであり、「道」とはその実践方法を示しています。お釈迦様は苦行にも快楽にも片寄らず悟りに至りました。
現代を生きる私たちは機械に頼る心(機心)から逃れることはできません。しかしそれにとらわれすぎ、そこから離れることばかり考えることも、また捉われの心なのです。技術革新は機心を起こす誘惑をはらんでいますが、私たちはその事をしっかり認識したうえで、仏教の説く「中道」という思いを心にとどめて、バランスの良い生活を送ることが大切です。
二〇二四(令和六)年 九月