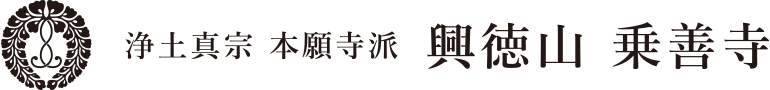あけましておめでとうございます。
皆さまにおかれましては、お念仏と共に新年をお迎えのこととお慶び申しあげます。
最近、宗教離れが進み、無宗教という方が多くいらっしゃいます。
その原因のひとつには核家族化もあろうかと思います。
今まで祖父母から自然と伝わっていたことが伝わりづらくなり、また、両親の共働きや子ども自身が習い事などで忙しくなっていることも要因となるのかも知れません。
いまの時代は、「効率化を求め、時短を求め、少しでも人と関わることを減らしてゆく」ことが優先されているように思います。
以前のように、「手塩にかけて、時間をかけて、人間関係を構築していく…」
そのような日本の美徳は失われつつあるように感じます。
宗教とは自分自身の生き方を示してくれるものです。
勘違いしがちなのは、宗教を「自分の願いを叶えてくれるもの」と考えていることです。
自分の願いを叶えてくれるか分からないなら信じない…
願いをかけたのに叶えてくれなかった…
そのように私利私欲の為に宗教があると考えるのならば、本当の宗教に出遇ってないといえるでしょう。
本当の宗教、特に仏教は、「思い通りにならないことに気づく教え」であります。
自らの愚かさを知らされる教えが仏教であり、知識を深め、偉く賢くなろうと仏法を聞くのではなく、仏教を学べば学ぶほど、知れば知るほど、自らの愚かさ、無力さ、恥ずかしさに気づかされるのです。
この世に生まれ、ただ泣くばかりの赤ちゃんが親に対して、「私を育ててください」とお願いすることはあり得ません。
お願いせずとも、頼まずとも、親は「元気に育ってよ」と赤ちゃんに願いをかけ育てるのです。親の願いが先、親の行動が先なのです。
自分中心でしか物事を見ることができない私に、願いをかけ続けてくださっていることに気づかせていただく中に、本当の幸せが見えてくるのでしょう。
無宗教と思っていた自分が、実はずっと仏教という生き方、価値観に自然と触れ、すでに願いの中にいたのだと気づかされることです。
私たちの生活の中に無宗教という事はあり得ません。
人とのつながり、いのちのつながり、自然とのつながり…
ひとりでは生きていけない私がここにいることに気づかされ、すべてが私を育ててくれるものであったと喜ばせていただくことこそ、宗教の生活と言えるのです。
本年もよろしくお願いいたします。